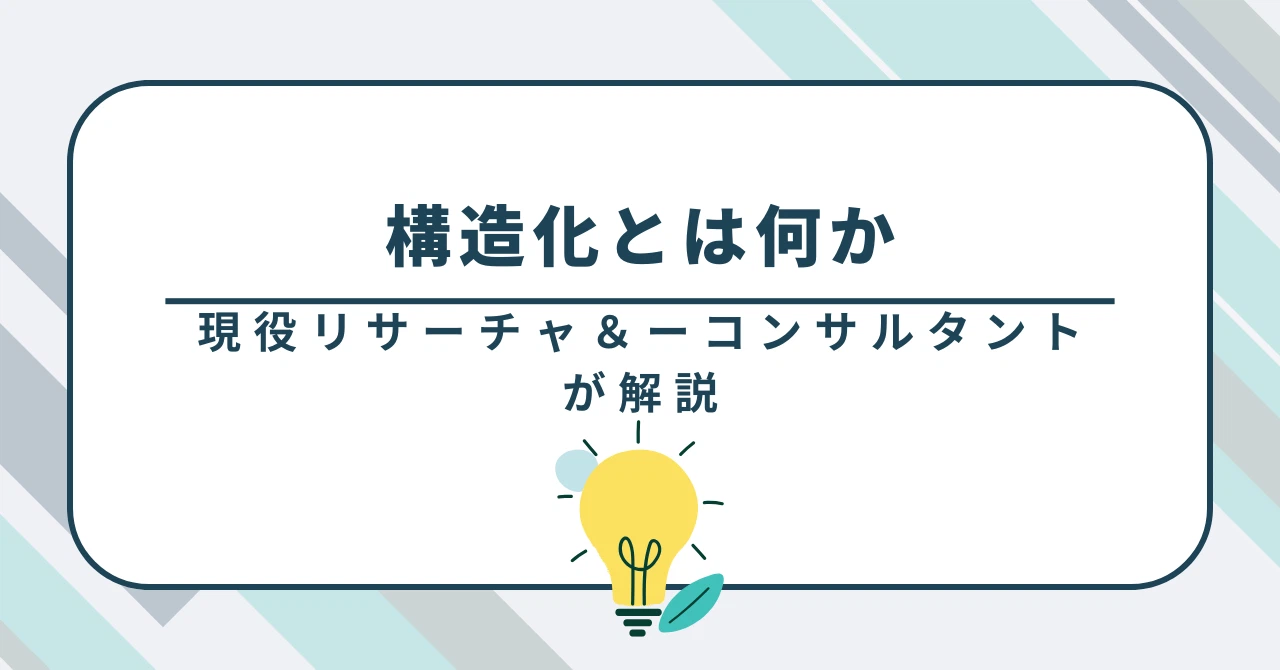構造化の目的
構造化の目的は
「複雑な情報を整理し、理解・伝達・意思決定をしやすくすること」です。
はじめに|なぜ“構造化”がスライド作りの決定打になるのか
社内向けプレゼンやクライアント提案書を前に、こんな悩みはありませんか?
- 「スライド 作り方」を検索してもテンプレばかりで、自分の情報が整理できない。
- プレゼン・資料の作り方のチェックリストを試すが、論点が散らかり説得力が弱い。
- パワーポイント中点プレゼンで文字が多く、聞き手が途中で離脱してしまう。
原因はシンプル── 情報整理(構造化)が甘い からです。構造化とは、膨大な情報を分解・整理・再構築し、PDCAサイクルで磨き込むプロセスそのもの。本稿では、構造化の手順を 「8ステップ+PDCAループ」 で紹介し、スライド/資料作成に直結させます。
構造化をするためにはどうすればよいか
構造化には大きく7つのステップがあります。
ゴールを一文で定義:誰が・いつまでに・何を判断するための資料か。
評価指標を仮決め:例)意思決定スピード、合意率、提案採択率。
まだ整理されていなくて構わない──未整理の多様な素材を確保せよ。
・判断を一時保留し、量を最優先。
・一次情報は原文ママで保存(ノイズを恐れない)。
・多視点・多ソース(社内データ、業界レポート、顧客インタビュー)。
・MECE原則で漏れなく重複なく分類。
・付箋・カードソートで“自然なまとまり”を発見。
・「その他」は禁止。分類できないなら切り口を増やす。
・因果・時系列・包含・対立──4つの基本構造でリンクを描く。
・点を線→面へ昇華させ、ストーリーの骨格を浮き彫りに。
上位概念 → 中位概念 → 具体例のピラミッド。抽象度を往復し、粒度を合わせる。
- トップダウン:Key message → Supporting points → Evidence。
- ボトムアップ検証:根拠データがメッセージを支えているか確認。
5‑1. スライド設計3原則
- シンプル:1スライド1メッセージ。
- ビジュアル:図解・アイコンで即理解。
- ノイズ比削減:余白を活かし、装飾は最低限。Presentation Zenの提唱する”High Signal‑to‑Noise Ratio”が指標となる(garrreynolds.com)。
5‑2. PowerPoint実装Tips
・ロジックツリー
・マトリックス
・プロセス図
- Whyを5回:各主張に「なぜ?」を連鎖させ、根拠の浅さを検知。
- DSRP視点で逆照合:Distinctions・Systems・Relationships・Perspectives 4観点で抜けを探す。
- ィードバックをタスク化し、次回のPlanに組み込む。
- ナレッジをテンプレート化し、チームで共有。
以降ステップごとに詳細に解説いたします。
PLAN|目的と指標を先に決める
まず最初に行うのは 「この資料は誰にどんな意思決定をさせるためのものか」 を一文で言い切る作業です。
続いて KPI(成果指標) を仮置きしましょう。意思決定速度、合意率、提案採択率など、後から振り返って「良し悪し」を測れる指標を2~3個セットにしておくと、作成途中で迷っても “指標に寄与するか否か” で判断できます。
最後に スコープの線引き を行います。扱わないテーマをあえて列挙すると、後の情報過多を防ぎ、チームメンバーとの認識齟齬も減らせます。
- ゴール未定のまま作業に入ると手戻り率が急上昇します。
時間と労力を守る最良の保険は「冒頭3行の宣言」です。
DO①|情報収集
ポイント:
・ソースを偏らせない
・“雑多でOK” のマインドセット
初心者が陥りがちなのは「手元にある社内データだけでなんとかしよう」とする姿勢です。これでは客観性に欠け、説得力の源泉が乏しくなります。定量データ(売上、アクセス解析)に加え、定性データ(顧客インタビュー、SNS口コミ)、さらには第三者のベンチマークデータ(業界レポート、学術論文)まで、最低3種類のソース を掛け合わせるのが基本形です。
また収集フェーズでは、情報の質より量を優先します。理由は単純で、分類・選別は後工程でいくらでもできる一方、取りこぼした情報は後から拾いにくいからです。クラウドに “収集用インボックス” を作り、出典・取得日だけタグ付けして、まずは思い切って放り込みましょう。ここでは「判断保留」がキーワードです。
DO②|カテゴリ化
収集した情報を眺めると、似通った内容同士が自然に寄り添い始めます。これを MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive) の発想でグルーピングします。付箋を使うなら、机いっぱいに貼り出して “親子関係” を探る感覚を大切にしてください。「その他」フォルダが生まれたら、それは切り口が曖昧なシグナルです。
KJ法やアフィニティダイアグラムなど形式ばった手法も有効ですが、最初は 「似ている」「関係がありそう」 と感じる直感を頼りにして構いません。グループが5~7個前後に収まると、人間の短期記憶に馴染みやすく、後の説明が格段にしやすくなります。
DO③|関係性の把握
ここからは “点” を “線” に変える作業です。具体的には、グループ間の 因果関係・時系列・包含関係・対立関係 を洗い出します。たとえば「売上低迷」という結果に対し、「広告費削減 → 認知度低下 → 新規顧客減少」という因果ループを矢印で示すと、一気にストーリーが生まれます。
時系列なら出来事を並べ、原因と結果なら矢印を引き、包含関係ならツリーを描きます。図を作り慣れていない場合は、ホワイトボードにマーカーで書き散らすだけでも十分効果があります。重要なのは “見える化” です。
このステップにより、情報の全体像が明確な骨格を持ち、論理性と伝達性が飛躍的に高まるのです。構造化の核心部分と言える重要な工程です。
DO④|階層構造の構築
関係性を把握したら、いよいよピラミッド原則を使って 結論 → 理由 → 根拠データ の流れを作ります。トップに置くのは “これだけは覚えて帰ってほしい” 一文。次の階層でその理由を2~4つ配置し、最下層には数値やグラフなど揺るぎない証拠を配置します。
この段階では “抽象と具体を行ったり来たり” するのがコツです。抽象度を上げすぎると説得力が薄まり、具体に寄りすぎると要点が散漫になりがちです。So What? / Why So? の2つの質問を自問自答し、結論と根拠の距離を詰めましょう。
- 各階層ごとに粒度を揃える(中位レベルで抽象度が混ざらないように)
- 階層が深くなりすぎる場合は再整理して情報の整理単位を見直す
- 上位概念から順にWhyで登って、Howで下りる構造が鉄則
DO⑤|表現と可視化
スライド作りに着手する際は、1スライド=1メッセージ を鉄則とします。文字を詰め込むより、図解・アイコン・色分けで視覚的ヒエラルキーを明確にしたほうが、読み手の理解と記憶に残りやすいからです。
PowerPoint では、まずスライドマスターでフォントと色を統一し、全ページに一貫したデザイン骨格を敷きましょう。そのうえで SmartArt の階層図やマトリクスを用いると、構造化で作ったロジックを “そのまま” 視覚に落とし込めます。余白は思っている以上に大きく取り、ポイントとなる数字やキーワードはフォントサイズを一段上げて強調するのが効果的です。
- 色やアイコンは意味と一致させる(例:重要度=赤、リスク=⚠️)
- パワポで作るときは1スライド1メッセージを意識
- 表現形式は「わかりやすさ」最優先で選ぶ(かっこよさではなく)
- ロジックツリー:論点の分解や因果関係の可視化に
- マトリクス表(2×2):分類構造やポジショニングに
- プロセスチャート / タイムライン:時間や工程の流れに
- ピラミッドストラクチャー:結論 → 根拠 → 具体の説明に
- マインドマップ:情報の包含関係や周辺論点を俯瞰する時に
CHECK|レビューで論理の“穴”を塞ぐ
スライドが形になったら、一度 制作者は黙って他者に読ませる のが最も有効なレビュー方法です。耳障りの良いフィードバックより、無言でページを行ったり来たりする動きのほうが “どこがわからないか” を雄弁に物語ります。
さらに So What? / Why So? / Only? / Data? / Flow? の5つの質問票を用意し、レビュアーに「気になった箇所に✔︎を付けてください」とお願いすると、論理漏れや根拠不足が可視化されます。自身でも Why を5回 問い直し、DSRP(Distinctions, Systems, Relationships, Perspectives)の4視点で “抜け” を探すと、ほぼ穴のない資料に仕上がります。抜けてる視点をAIに補ってもらうといいかもしれません。
ACT|改善点を次サイクルへ
レビューで得た示唆を AAR(After‑Action Review) で整理します。ここでは「想定した結果」「実際に起きたこと」「差分の原因」「次に活かす行動」の4項目を表形式にまとめ、チームの共有ドライブや Wiki に格納しましょう。テンプレートにしておくと、同じミスを2度繰り返す確率が激減します。
最後に、次回の PLAN をすぐにカレンダーに登録しておくと、PDCA が途切れず、組織に学習サイクルが根付きます。改善点を書き出すだけで終わらせず、「いつ・誰が・何を実行するか」を決めて初めて “ACT” が完了します。
まとめ|構造化×PDCAで資料作成を“作業”から“価値創造”へ
構造化は情報整理の技法であると同時に、ビジネス成果を最大化する“思考インフラ”です。混沌を恐れず、まず分解し、再構築し、そしてPDCAで磨き上げる——それこそが説得力あるプレゼンへの最短ルートです。
単に情報を並べるのではなく、「意味を見出し、構造を与え、伝わる形にする」ことが、構造化の真髄です。