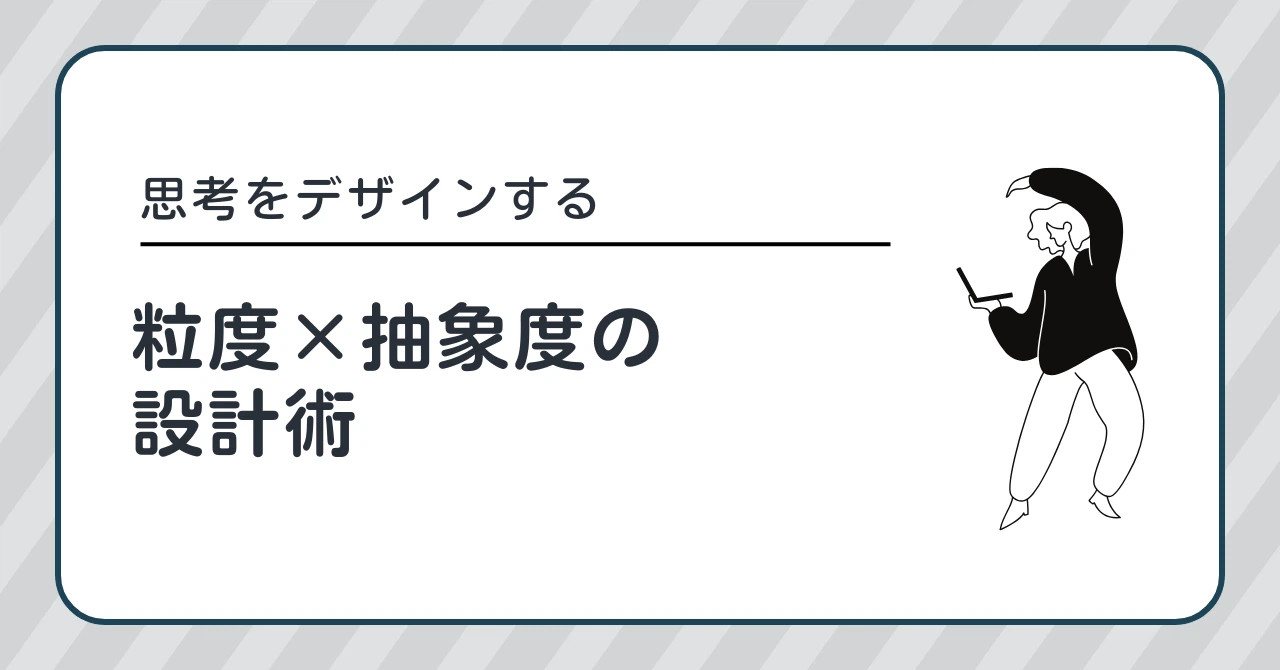目次
はじめに|なぜ粒度コントロールが鍵か
- 当ブログでは六型(階層/順序/循環/比較/因果/推移)と三領域(視点)を掛け合わせたフレームワークを提示し、情報整理の“漏れ”を塞いできた。
- しかし“どの深さで語るか”を定める 粒度(granularity) と 抽象度(abstraction level) に指針は示していない。
- ピラミッドストラクチャーが示すように、上位は要点、下位はエビデンスという階層構造そのものが
“粒度コントロール”である。
視点は“どこを見るか”、粒度は“どれくらい拡大・縮小するか”。両輪が揃って初めて情報は動線を持つ。
1. 粒度の三層モデル(Macro / Mid / Micro)
| 層 | 目的 | 典型アウトプット | 情報量目安 |
|---|---|---|---|
| マクロ | 全体像の提示・意思決定者への要約 | エグゼクティブサマリ、1枚図、北極星指標 | 1〜2 % |
| ミドル | 章ごとの骨格・議論のロードマップ | 章立て、目次、論点マップ | 10〜15 % |
| ミクロ | 証拠・演繹・データ | 解析結果、原表、インタビュー逐語録 | 83〜89 % |
- マクロ:経営層は「結論→理由→証拠」のトップダウンで情報を摂取する習性がある。
- ミドル:読者が“迷わない階段”を設計する層。各章が MECE に並ぶことが必須条件。
- ミクロ:UXの世界では“チャンク”単位で提示すると理解・記憶が向上する。
ミクロをいきなり提示するのは、旅のしおり無しで「成田からサンパウロまで自力でどうぞ」と言うようなものです。
2. 抽象度調整 5 ステップ
STEP
目的の再確認
誰の、どんな意思決定を支援するかを 1 文で言い切る
STEP
読者ペルソナ設定
組織階層・専門度・可処分時間を明文化
STEP
最低限のマクロ設計
結論・主要論点・エビデンスの位置関係をピラミッドに配置
STEP
必要箇所だけミクロ展開
「根拠を問われる可能性が高い論点」に絞って深堀り
STEP
リンクで階層接続
スライドやドキュメント内ハイパーリンク、図形ナビゲーションで“往復切符”を実装
3. 六型 × 粒度 対応表
| 六型 | 得意粒度 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 階層(ピラミッド) | マクロ | 戦略要約、投資判断 |
| 流れ(順序) | ミドル | プロセス設計、ロードマップ |
| 循環(ループ) | ミドル | PDCA、システム思考 |
| 比較(配置) | ミドル→ミクロ | ベンチマーク、優先度決定 |
| 因果(ネットワーク) | ミクロ | リスク要因解析、施策相関 |
| 推移(時系列) | マクロ→ミドル | KPI 変化、変革ストーリー |
【事実】
- ピラミッドは上位抽象化の視覚化ツールであり、最上層メッセージを圧縮しやすい。
- 因果はデータ粒度が細かいほど精度が上がるためミクロ寄り。
4. 導入チェックリスト(Before/After)
| 質問 | Before(導入前の兆候) | After(導入後の変化) |
|---|---|---|
| 結論は 1 ページで伝わるか | 3 ページ目まで“前置き” | 1 スライド目で核心 |
| 読者が「で、何が言いたい?」と聞くか | 頻出 | 激減 |
| 詳細を聞かれたとき即リンクできるか | スクロール探し | ハイパーリンク一発 |
| ドキュメントサイズ | 無駄な重複多数 | 20〜30 % 削減 |
| 打合せ時間 | 60 分フル消費 | 40 分で決着、20 分浮く |
チェックのコツ:会議後に「要するに◯◯ですね」と言われたら After。